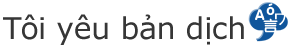- Văn bản
- Lịch sử
436 松山大学論集 第17巻 第2号用林産物需給動態調査によると,製
436 松山大学論集 第17巻 第2号
用林産物需給動態調査によると,製炭者数は197人に減少している。 図6は,紀州備長炭の生産の多い和歌山県の中・南部の市町村別の最近40
年間の製炭者の減少状況を示しているものである。 製炭者数の最も多い南部川村に例をとると,1960年には111の自営製炭世
帯を数えたが,1999年には48世帯となっており,2004年には25世帯と半減 している。1999年から2004年の間に,製炭業から脱落した世帯をみると,製 炭者が高齢化したもの10世帯,同死亡したもの4世帯,同病気となったもの
図6 和歌山県の製炭者の市町村別の減少状況(1960~2003年)
中津村
県 界
市町村界
川辺町
竜神村
印南町
南部川村
中辺路町
100人
50
10
1
1960年の自営製炭世帯
田辺市
大塔村
古座川町
那智勝浦町
2003年の木炭生産者数
日置川町 すさみ町
古座町
0 20d
注)1960年の製炭者数は1960年農林業センサスの市町村別統計書(和歌山県)の自営製炭 世帯。2003年の製炭者数は和歌山県の特殊林産物需給動態調査の木炭生産者数による。
都市住民の山村移住による備長炭の技術伝承 437
1世帯,同梅栽培に転向18)したもの6世帯,製炭者が出身地に帰郷したもの
1世帯,不明が1世帯となっている。隣接の田辺市秋津川地区も同様の傾向で ある。
(イ) 都市住民の山村移住
それでは,このような製炭者の減少はどのように補充されているのであろう か。すでに第2章でも述べたように,和歌山の農林水産行政の一環としての農 山村への都市住民の定住政策と,各市町村で行っている製炭業に新規参入する 者に対する技術指導,あるいは定住政策が,各市町村で行われていることが,製 炭業への新規参入を招来し,製炭業の担い手の養成となっているのである。
和歌山県の紀州備長炭参入者の資料によると,1989年(平成元)から2004 年の紀州備長炭新規参入者は87名に達し,都市域から農山村への U ターン者 が46%,都市域からの和歌山県の都
市域への J ターンが6.9%,都市域か ら身寄りの ない農山村の I ターンが 41.4%となっている。
市町村別の紀州備長炭への新規参入 者数は表4に示すが,これによると, 南部川村の16人をはじめ,中津村・ 田辺市・大塔村などに紀州備長炭への 新規参入者の多いことがわかる。一 方,紀州備長炭への新規参入者を送り 出す地域をみると,和歌山県(46人) 以外では隣接する京阪神区が最も多 く,次いで首都圏,福岡県などが多い といえる。
表4 紀州備長炭の市町村別新規参入者数
市町村名 新規参入者数
南 部 川 村 16
中 津 村 13
田 辺 市 12
大 塔 村 11
日 置 川 町 8
川 辺 町 7
南 部 町 6
中 辺 路 町 4
那智勝浦町 3
白 浜 町 2
印 南 町 2
す さ み 町 2
龍 神 町 2
その他町村 11
合 計 99
注)和歌山県定住促進課資料による。 転入者数は平成元年~14年の分。 うち12名は廃業等で製炭を中止した。
438 松山大学論集 第17巻 第2号
図7 紀州備長炭新規参入者の出身地(1989~2003年)
0 200d
50人
10
1
注)和歌山県農林水産物定住促進課提供資料より作成
都市住民の山村移住による備長炭の技術伝承 439
(ウ) 従来の製炭形態
紀州備長炭の製造は,従来どのように行われていたのであろうか。図8は, 約35町歩の山林を所有し,主として○ア10町歩・○イ 9町歩の択伐林にて原木を 調達している秋津川地区の N 氏の自山の択伐林経営を示すものである。択伐 林には弱度・中庸・強度択伐の3様式があったが,図9はそのなかで中庸度の 択伐林を示す。中庸度択伐林は,林積で60~70%,本数で20~30%,目通り 直径4.5 以上の樹木が択伐の対象となる。回帰年は8~10年,林層は三段林 をなす。択伐林は幼齢木・中齢木を伐採せず,伐採周期が短いので,皆伐林に 比較して,同一年間に50~60%の増収穫を得ることができた。当時,紀州備 長炭の核心的生産地であった秋津川地区のウバメガシの択伐の技術は,全国の 最高水準19)にあったといえる。
しかしながら和歌山県中部の山村は,大山林地主による林野の集積が激し く,日本の代表的大山林地主の出現地20)であった。明治以降は臨海部の薪炭 商などに林野が集積され,製炭者の多くは自己所有林が狭小であり,原木を大 山林地主の薪炭山に依存せざるを得ず,焼子制度21)のもとに製炭に従事する 者が多かった。
図10は南部川村市井川の H 氏が入山している買山(立木のみ買得)におけ る薪炭山の利用実態を示すものである。炭山の面積は約5町歩,木炭の産出量 は約1,000俵(15 )の山であり,炭窯や居小屋,サデ道は買山した製炭者に よって,順次利用されていくという。1960年代までは,紀州備長炭の産地で
は,炭窯は山中のウバメガシの集材に便利な場所と,沢があり水に便利なとこ
ろに構築された。沢に穿たれたえぶりつぼには,えぶりなどの木製用具などが
水に浸され,白炭の消火に際しては素灰にその水が散水され,また非常時の防
い ご や
火用水にも使われた。居小屋は精 (ねらし)の時などは,そこに起居すると
共に,製炭作業中の休憩所ともなった。
440 松山大学論集 第17巻 第2号
図8 和歌山県 N 氏の択伐薪炭林の経営(1965年)
11町歩の山林 3町歩の択伐薪炭林
8町歩のスギ・ヒノキ造林
2.5町歩の山林 赤松・スギの造林
9町歩の 択伐薪炭林
010町歩の 択伐薪炭林
®
2町歩の山林 1.2町歩のヒノキ造林
0.8町歩の皆伐薪炭林
® ® C
0 500c
河 川
道 路
~ 将来の伐採順 炭 窯
N氏の所有林
注)篠原重則(1967年):四国地方の製炭地域の類型,地理学評論,40-11による。
ウバメガシ
ザツ
図9 和歌山県秋津川の択伐林
萌芽 8~10年
8~10年 8~10年
択伐2年後の林相 次回択伐2年後の林相 次々回択伐2年後の林相 25年程度
注)篠原重則(1967年):四国地方の製炭地域の類型,地理学評論,40-11による。
都市住民の山村移住による備長炭の技術伝承 441
図10 南部川村市井川の H 氏の買山(見取図)
サ
サ サ デ
デ デ 道
道 道
旧窯跡 尾
根
旧窯跡
架
線 沢 サ
木馬道 デ
道
えぶりつぼ
居小屋
炭窯
H氏の自宅
小川
車 道
442 松山大学論集 第17巻 第2号
写真7 南部川村市井川における山中の炭窯(左)と居小 屋(右端)(2004年3月)
写真8 南部川村市井川におけるえぶりつぼ
(2004年3月)
(エ) 備長炭生産の現状
南部川村は2002年現在37名の製炭者が存在し,木炭生産量,製炭者数にお いて,和歌山県下随一の市町村である。筆者は2003年から2004年にかけて, 各炭窯に製炭者を訪ね,製炭者の製炭活動の実態と日常生活について実態調査 を試みた。調査回数は延べ5回に及んだが,うち32名の製炭者から聞取り調 査をすることができた。図11は,その32名(地元製炭者24名,都市部から の新規参入者8名)の炭窯と住居,原木山を地図上に示したものである。この
都市住民の山村移住による備長炭の技術伝承 443
うち原木山に炭窯を構築しているのは の製炭者のみであった。同氏の購入し ている薪炭山(原木のみ購入)の経営と自宅の関係は,図10に示していると ころである。それ以外の炭窯は国道沿い,県道・町道・林道沿いにあり,それ は軽四トラックで原木を搬入するのに便利な地点に立地しているといえる。製 炭者が軽四トラックを導入しだしたのは1970年ころからであり,炭窯が道路 沿いに主として立地しだしたのは,その後1980年ころからであるという。
炭窯と製炭者の住居は近隣しているものもあるが1 から数 離れているも のが多い。炭窯が人里離れた道路沿いに立地するのは,製炭作業中の木炭の煙 を住民が嫌うことによる。
炭窯と原木山はおおむね離れている。それは製炭者の山林所有が皆無であっ
図11 南部川村の製炭者の炭窯・住居・原木採取林の分布(2003年)
678c
768c
603c
24
422c
4
24
22
22 28
29
28
2121 3
3 25
1 1
4
22 29
6 49 8 10 18
27 8 2620
1918
23
1615
14
6 27
9 26 20
10 10
17 2319
25 17
386c
7
30 15
30 413c
2
26
511c
499c
都市移住民の炭窯
339c 21
31
24 13
11
5 347c
13 9
地元住民の炭窯
製炭者の住居
12 12
125c
1
注)実地調査によって作成
20
15
264c
0 2d
原木山(立木購入)
原木山(自山) 国道 県道・町村道 河川
山麓線
番号は製炭者番号を示す(同一製炭者については,炭窯・住居・原木採取林ともに同一 番号を使用している)。
444 松山大学論集 第17巻 第2号
たり,極めて小規模所有であることによる。製炭者は原木山が移動するたび に,炭窯を再構築するとすれば資金と労力を多く要する。炭窯が原木山に規制 されなくなったのは,軽四トラックが普及し,原木が容易に炭窯まで運搬でき るようになったからである。
原木の入手方法は,購入した買山で,製炭者自身が伐採し,それを軽四トラッ クで窯元まで運搬するものもあるが,村内外の原木業者から購入するものもあ る。製炭能率を上げるためには,原木の伐採・搬出をするよりも,立木購入に 依存する方が,木炭の販売生産量を伸ばせるという。
(オ) 都市住民の紀州備長炭生産への新規参入者の実態
都市住民の紀州備長炭への新規参入者は,和歌山県定住促進課の資料による と,1984年から2004年の間に87名に達し,U ターン・I ターン併せて87名 に達した。製炭業への新規参入者が多い和歌山県の市町村は,南部川村22)・中 津村23)・田辺市24)・大塔村の和歌山県の中部山村地域であることは,既に指摘 したところである。表5は製炭業への新規参入者の多い4市町村の新規参入者 の前住地と移住年,移住動機などを一覧表としてまとめたものである。紀州備 長炭に新規参入前の前住地
は,大阪を中心とした近畿 大都市圏,東京を中心とし た首都圏に多く,次いで東 海圏であるといえる。年齢 層 を みる と,70歳を超え る高齢者から,青壮年層ま で多岐にわたっている。前 住地の都市部での職業は多
岐にわたるが,コンピュー タ技師・銀行員・学習塾の
写真9 田辺市秋津川の紀州備長炭記念公園
(2003年11月)
手前は物産館-道の駅-,向こうは資料館
都市住民の山村移住による備長炭の技術伝承 445
講師など,精神的ストレスの高い職業に従事していた者が目立ち,その他,近 代工場で流れ作業的仕事に従事していたものが多い。
備長炭の製炭に魅せられた動機は,窯出し時の真赤に燃えさかる炎に魅せら れた者が多いが,本質的には,自然に恵まれた山村の生活に憧れ,農林業で自 活することに生き甲斐を目ざす者が圧倒的に多いといえる。このようにみる と,かつては農山村から大都市域に就業を求める住民の移動が主流であった が,今や逆に大都市域から
農山村への人口の還流が見 られるのである。大都市の 大企業に雇用されて厳しい 管理社会に生きるのではな く,自然に恵まれた農山村 で自活し,のんびりと暮ら すことに生き甲斐を見出す 都市住民が確実に増加して
いることを読みとることが できる。
彼等は同伴者を伴って入 村する者が多いのも一つの 特色である。山村の在地の 後継者が嫁不足に悩むのと は対照的である。大都市域 からよき伴侶を伴って入村 し,在地の独身の青壮年者 を羨ましがらせている有様
0/5000
436 Matsuyama University review vol. 17 No. 2According to the supply and demand for forest products research, charcoal toll has declined to 197. Figure 6 the municipality recently in southern Wakayama Prefecture Kishu binchotan charcoal production of 40That shows a status of charcoal per year. Take the example of charcoal by the most southern Kawamura, and self-employed charcoal of 111 in 1960In 1999 has become 48 households, counting zone, and 25 households in 2004 has reduced by half. Households in 1999 during the year 2004, dropped from the charcoal trade, and made charcoal by aging of 10 households, the deaths that made 4 families, hospital care andMunicipality status of charcoal Figure 6 Wakayama Prefecture (1960-2003) Nakatsu, Wakayama County boundaryMunicipal boundaries Kawanabe-Cho,Ryujin village Inami-Cho Minabegawa, Wakayama Nakahechi, Wakayama 100 people50101In 1960, self-employed charcoal household Tanabe Daito village Kozagawa Nachi-Katsuura town The number of charcoal producers in 2003 Hikigawa, susami, Wakayama Koza0 20 dNote) charcoal toll 1960 1960 census municipality by self-made charcoal household statistical (Wakayama Prefecture). Charcoal toll in 2003, according to the charcoal producers of special forest products supply and demand investigation of Wakayama Prefecture. Bincho charcoal by the migration of city dwellers of the technology transfer 4371世帯,同梅栽培に転向18)したもの6世帯,製炭者が出身地に帰郷したもの1世帯,不明が1世帯となっている。隣接の田辺市秋津川地区も同様の傾向で ある。(イ) 都市住民の山村移住それでは,このような製炭者の減少はどのように補充されているのであろう か。すでに第2章でも述べたように,和歌山の農林水産行政の一環としての農 山村への都市住民の定住政策と,各市町村で行っている製炭業に新規参入する 者に対する技術指導,あるいは定住政策が,各市町村で行われていることが,製 炭業への新規参入を招来し,製炭業の担い手の養成となっているのである。和歌山県の紀州備長炭参入者の資料によると,1989年(平成元)から2004 年の紀州備長炭新規参入者は87名に達し,都市域から農山村への U ターン者 が46%,都市域からの和歌山県の都 市域への J ターンが6.9%,都市域か ら身寄りの ない農山村の I ターンが 41.4%となっている。市町村別の紀州備長炭への新規参入 者数は表4に示すが,これによると, 南部川村の16人をはじめ,中津村・ 田辺市・大塔村などに紀州備長炭への 新規参入者の多いことがわかる。一 方,紀州備長炭への新規参入者を送り 出す地域をみると,和歌山県(46人) 以外では隣接する京阪神区が最も多 く,次いで首都圏,福岡県などが多い といえる。 表4 紀州備長炭の市町村別新規参入者数市町村名 新規参入者数南 部 川 村 16中 津 村 13田 辺 市 12大 塔 村 11日 置 川 町 8川 辺 町 7南 部 町 6中 辺 路 町 4那智勝浦町 3白 浜 町 2印 南 町 2す さ み 町 2龍 神 町 2その他町村 11合 計 99注)和歌山県定住促進課資料による。 転入者数は平成元年~14年の分。 うち12名は廃業等で製炭を中止した。 438 松山大学論集 第17巻 第2号図7 紀州備長炭新規参入者の出身地(1989~2003年) 0 200d 50人101 注)和歌山県農林水産物定住促進課提供資料より作成 都市住民の山村移住による備長炭の技術伝承 439(ウ) 従来の製炭形態紀州備長炭の製造は,従来どのように行われていたのであろうか。図8は, 約35町歩の山林を所有し,主として○ア10町歩・○イ 9町歩の択伐林にて原木を 調達している秋津川地区の N 氏の自山の択伐林経営を示すものである。択伐 林には弱度・中庸・強度択伐の3様式があったが,図9はそのなかで中庸度の 択伐林を示す。中庸度択伐林は,林積で60~70%,本数で20~30%,目通り 直径4.5 以上の樹木が択伐の対象となる。回帰年は8~10年,林層は三段林 をなす。択伐林は幼齢木・中齢木を伐採せず,伐採周期が短いので,皆伐林に 比較して,同一年間に50~60%の増収穫を得ることができた。当時,紀州備 長炭の核心的生産地であった秋津川地区のウバメガシの択伐の技術は,全国の 最高水準19)にあったといえる。しかしながら和歌山県中部の山村は,大山林地主による林野の集積が激し く,日本の代表的大山林地主の出現地20)であった。明治以降は臨海部の薪炭 商などに林野が集積され,製炭者の多くは自己所有林が狭小であり,原木を大 山林地主の薪炭山に依存せざるを得ず,焼子制度21)のもとに製炭に従事する 者が多かった。図10は南部川村市井川の H 氏が入山している買山(立木のみ買得)におけ る薪炭山の利用実態を示すものである。炭山の面積は約5町歩,木炭の産出量 は約1,000俵(15 )の山であり,炭窯や居小屋,サデ道は買山した製炭者に よって,順次利用されていくという。1960年代までは,紀州備長炭の産地では,炭窯は山中のウバメガシの集材に便利な場所と,沢があり水に便利なとこ ろに構築された。沢に穿たれたえぶりつぼには,えぶりなどの木製用具などが水に浸され,白炭の消火に際しては素灰にその水が散水され,また非常時の防い ご や 火用水にも使われた。居小屋は精 (ねらし)の時などは,そこに起居すると共に,製炭作業中の休憩所ともなった。 440 松山大学論集 第17巻 第2号図8 和歌山県 N 氏の択伐薪炭林の経営(1965年) 11町歩の山林 3町歩の択伐薪炭林8町歩のスギ・ヒノキ造林 2.5町歩の山林 赤松・スギの造林 9町歩の 択伐薪炭林 010町歩の 択伐薪炭林 ® 2町歩の山林 1.2町歩のヒノキ造林0.8町歩の皆伐薪炭林 ® ® C 0 500c 河 川道 路~ 将来の伐採順 炭 窯N氏の所有林 注)篠原重則(1967年):四国地方の製炭地域の類型,地理学評論,40-11による。
ウバメガシ
ザツ
図9 和歌山県秋津川の択伐林
萌芽 8~10年
8~10年 8~10年
択伐2年後の林相 次回択伐2年後の林相 次々回択伐2年後の林相 25年程度
注)篠原重則(1967年):四国地方の製炭地域の類型,地理学評論,40-11による。
都市住民の山村移住による備長炭の技術伝承 441
図10 南部川村市井川の H 氏の買山(見取図)
サ
サ サ デ
デ デ 道
道 道
旧窯跡 尾
根
旧窯跡
架
線 沢 サ
木馬道 デ
道
えぶりつぼ
居小屋
炭窯
H氏の自宅
小川
車 道
442 松山大学論集 第17巻 第2号
写真7 南部川村市井川における山中の炭窯(左)と居小 屋(右端)(2004年3月)
写真8 南部川村市井川におけるえぶりつぼ
(2004年3月)
(エ) 備長炭生産の現状
南部川村は2002年現在37名の製炭者が存在し,木炭生産量,製炭者数にお いて,和歌山県下随一の市町村である。筆者は2003年から2004年にかけて, 各炭窯に製炭者を訪ね,製炭者の製炭活動の実態と日常生活について実態調査 を試みた。調査回数は延べ5回に及んだが,うち32名の製炭者から聞取り調 査をすることができた。図11は,その32名(地元製炭者24名,都市部から の新規参入者8名)の炭窯と住居,原木山を地図上に示したものである。この
都市住民の山村移住による備長炭の技術伝承 443
うち原木山に炭窯を構築しているのは の製炭者のみであった。同氏の購入し ている薪炭山(原木のみ購入)の経営と自宅の関係は,図10に示していると ころである。それ以外の炭窯は国道沿い,県道・町道・林道沿いにあり,それ は軽四トラックで原木を搬入するのに便利な地点に立地しているといえる。製 炭者が軽四トラックを導入しだしたのは1970年ころからであり,炭窯が道路 沿いに主として立地しだしたのは,その後1980年ころからであるという。
炭窯と製炭者の住居は近隣しているものもあるが1 から数 離れているも のが多い。炭窯が人里離れた道路沿いに立地するのは,製炭作業中の木炭の煙 を住民が嫌うことによる。
炭窯と原木山はおおむね離れている。それは製炭者の山林所有が皆無であっ
図11 南部川村の製炭者の炭窯・住居・原木採取林の分布(2003年)
678c
768c
603c
24
422c
4
24
22
22 28
29
28
2121 3
3 25
1 1
4
22 29
6 49 8 10 18
27 8 2620
1918
23
1615
14
6 27
9 26 20
10 10
17 2319
25 17
386c
7
30 15
30 413c
2
26
511c
499c
都市移住民の炭窯
339c 21
31
24 13
11
5 347c
13 9
地元住民の炭窯
製炭者の住居
12 12
125c
1
注)実地調査によって作成
20
15
264c
0 2d
原木山(立木購入)
原木山(自山) 国道 県道・町村道 河川
山麓線
番号は製炭者番号を示す(同一製炭者については,炭窯・住居・原木採取林ともに同一 番号を使用している)。
444 松山大学論集 第17巻 第2号
たり,極めて小規模所有であることによる。製炭者は原木山が移動するたび に,炭窯を再構築するとすれば資金と労力を多く要する。炭窯が原木山に規制 されなくなったのは,軽四トラックが普及し,原木が容易に炭窯まで運搬でき るようになったからである。
原木の入手方法は,購入した買山で,製炭者自身が伐採し,それを軽四トラッ クで窯元まで運搬するものもあるが,村内外の原木業者から購入するものもあ る。製炭能率を上げるためには,原木の伐採・搬出をするよりも,立木購入に 依存する方が,木炭の販売生産量を伸ばせるという。
(オ) 都市住民の紀州備長炭生産への新規参入者の実態
都市住民の紀州備長炭への新規参入者は,和歌山県定住促進課の資料による と,1984年から2004年の間に87名に達し,U ターン・I ターン併せて87名 に達した。製炭業への新規参入者が多い和歌山県の市町村は,南部川村22)・中 津村23)・田辺市24)・大塔村の和歌山県の中部山村地域であることは,既に指摘 したところである。表5は製炭業への新規参入者の多い4市町村の新規参入者 の前住地と移住年,移住動機などを一覧表としてまとめたものである。紀州備 長炭に新規参入前の前住地
は,大阪を中心とした近畿 大都市圏,東京を中心とし た首都圏に多く,次いで東 海圏であるといえる。年齢 層 を みる と,70歳を超え る高齢者から,青壮年層ま で多岐にわたっている。前 住地の都市部での職業は多
岐にわたるが,コンピュー タ技師・銀行員・学習塾の
写真9 田辺市秋津川の紀州備長炭記念公園
(2003年11月)
手前は物産館-道の駅-,向こうは資料館
都市住民の山村移住による備長炭の技術伝承 445
講師など,精神的ストレスの高い職業に従事していた者が目立ち,その他,近 代工場で流れ作業的仕事に従事していたものが多い。
備長炭の製炭に魅せられた動機は,窯出し時の真赤に燃えさかる炎に魅せら れた者が多いが,本質的には,自然に恵まれた山村の生活に憧れ,農林業で自 活することに生き甲斐を目ざす者が圧倒的に多いといえる。このようにみる と,かつては農山村から大都市域に就業を求める住民の移動が主流であった が,今や逆に大都市域から
農山村への人口の還流が見 られるのである。大都市の 大企業に雇用されて厳しい 管理社会に生きるのではな く,自然に恵まれた農山村 で自活し,のんびりと暮ら すことに生き甲斐を見出す 都市住民が確実に増加して
いることを読みとることが できる。
彼等は同伴者を伴って入 村する者が多いのも一つの 特色である。山村の在地の 後継者が嫁不足に悩むのと は対照的である。大都市域 からよき伴侶を伴って入村 し,在地の独身の青壮年者 を羨ましがらせている有様
ウバメガシ
ザツ
図9 和歌山県秋津川の択伐林
萌芽 8~10年
8~10年 8~10年
択伐2年後の林相 次回択伐2年後の林相 次々回択伐2年後の林相 25年程度
注)篠原重則(1967年):四国地方の製炭地域の類型,地理学評論,40-11による。
都市住民の山村移住による備長炭の技術伝承 441
図10 南部川村市井川の H 氏の買山(見取図)
サ
サ サ デ
デ デ 道
道 道
旧窯跡 尾
根
旧窯跡
架
線 沢 サ
木馬道 デ
道
えぶりつぼ
居小屋
炭窯
H氏の自宅
小川
車 道
442 松山大学論集 第17巻 第2号
写真7 南部川村市井川における山中の炭窯(左)と居小 屋(右端)(2004年3月)
写真8 南部川村市井川におけるえぶりつぼ
(2004年3月)
(エ) 備長炭生産の現状
南部川村は2002年現在37名の製炭者が存在し,木炭生産量,製炭者数にお いて,和歌山県下随一の市町村である。筆者は2003年から2004年にかけて, 各炭窯に製炭者を訪ね,製炭者の製炭活動の実態と日常生活について実態調査 を試みた。調査回数は延べ5回に及んだが,うち32名の製炭者から聞取り調 査をすることができた。図11は,その32名(地元製炭者24名,都市部から の新規参入者8名)の炭窯と住居,原木山を地図上に示したものである。この
都市住民の山村移住による備長炭の技術伝承 443
うち原木山に炭窯を構築しているのは の製炭者のみであった。同氏の購入し ている薪炭山(原木のみ購入)の経営と自宅の関係は,図10に示していると ころである。それ以外の炭窯は国道沿い,県道・町道・林道沿いにあり,それ は軽四トラックで原木を搬入するのに便利な地点に立地しているといえる。製 炭者が軽四トラックを導入しだしたのは1970年ころからであり,炭窯が道路 沿いに主として立地しだしたのは,その後1980年ころからであるという。
炭窯と製炭者の住居は近隣しているものもあるが1 から数 離れているも のが多い。炭窯が人里離れた道路沿いに立地するのは,製炭作業中の木炭の煙 を住民が嫌うことによる。
炭窯と原木山はおおむね離れている。それは製炭者の山林所有が皆無であっ
図11 南部川村の製炭者の炭窯・住居・原木採取林の分布(2003年)
678c
768c
603c
24
422c
4
24
22
22 28
29
28
2121 3
3 25
1 1
4
22 29
6 49 8 10 18
27 8 2620
1918
23
1615
14
6 27
9 26 20
10 10
17 2319
25 17
386c
7
30 15
30 413c
2
26
511c
499c
都市移住民の炭窯
339c 21
31
24 13
11
5 347c
13 9
地元住民の炭窯
製炭者の住居
12 12
125c
1
注)実地調査によって作成
20
15
264c
0 2d
原木山(立木購入)
原木山(自山) 国道 県道・町村道 河川
山麓線
番号は製炭者番号を示す(同一製炭者については,炭窯・住居・原木採取林ともに同一 番号を使用している)。
444 松山大学論集 第17巻 第2号
たり,極めて小規模所有であることによる。製炭者は原木山が移動するたび に,炭窯を再構築するとすれば資金と労力を多く要する。炭窯が原木山に規制 されなくなったのは,軽四トラックが普及し,原木が容易に炭窯まで運搬でき るようになったからである。
原木の入手方法は,購入した買山で,製炭者自身が伐採し,それを軽四トラッ クで窯元まで運搬するものもあるが,村内外の原木業者から購入するものもあ る。製炭能率を上げるためには,原木の伐採・搬出をするよりも,立木購入に 依存する方が,木炭の販売生産量を伸ばせるという。
(オ) 都市住民の紀州備長炭生産への新規参入者の実態
都市住民の紀州備長炭への新規参入者は,和歌山県定住促進課の資料による と,1984年から2004年の間に87名に達し,U ターン・I ターン併せて87名 に達した。製炭業への新規参入者が多い和歌山県の市町村は,南部川村22)・中 津村23)・田辺市24)・大塔村の和歌山県の中部山村地域であることは,既に指摘 したところである。表5は製炭業への新規参入者の多い4市町村の新規参入者 の前住地と移住年,移住動機などを一覧表としてまとめたものである。紀州備 長炭に新規参入前の前住地
は,大阪を中心とした近畿 大都市圏,東京を中心とし た首都圏に多く,次いで東 海圏であるといえる。年齢 層 を みる と,70歳を超え る高齢者から,青壮年層ま で多岐にわたっている。前 住地の都市部での職業は多
岐にわたるが,コンピュー タ技師・銀行員・学習塾の
写真9 田辺市秋津川の紀州備長炭記念公園
(2003年11月)
手前は物産館-道の駅-,向こうは資料館
都市住民の山村移住による備長炭の技術伝承 445
講師など,精神的ストレスの高い職業に従事していた者が目立ち,その他,近 代工場で流れ作業的仕事に従事していたものが多い。
備長炭の製炭に魅せられた動機は,窯出し時の真赤に燃えさかる炎に魅せら れた者が多いが,本質的には,自然に恵まれた山村の生活に憧れ,農林業で自 活することに生き甲斐を目ざす者が圧倒的に多いといえる。このようにみる と,かつては農山村から大都市域に就業を求める住民の移動が主流であった が,今や逆に大都市域から
農山村への人口の還流が見 られるのである。大都市の 大企業に雇用されて厳しい 管理社会に生きるのではな く,自然に恵まれた農山村 で自活し,のんびりと暮ら すことに生き甲斐を見出す 都市住民が確実に増加して
いることを読みとることが できる。
彼等は同伴者を伴って入 村する者が多いのも一つの 特色である。山村の在地の 後継者が嫁不足に悩むのと は対照的である。大都市域 からよき伴侶を伴って入村 し,在地の独身の青壮年者 を羨ましがらせている有様
đang được dịch, vui lòng đợi..


436 Matsuyama University Journal 17 Volume No. 2 According to the supply and demand for forest products dynamics research, manufacturing charcoal's number has decreased to 197 people. 6, Kishu charcoal of many Wakayama Prefecture in-southern part of the municipality another recent 40 productivity is one that shows a decrease in the status of manufacturing charcoal's years. Taking the example most often Minabegawa village of manufacturing charcoal's number, self-employed made Sumiyo of the 1960 111 have been counted the band, in 1999 and has become a 48 households, in 2004 and 25 households half are doing. In 1999 to 2004, looking at the households that dropped out of the manufacturing coal industry, manufacturing charcoal's 10 households those aging, 4 households those same death, what was the same illness manufacturing in FIG. 6, Wakayama Prefecture coal's municipal reduction situation (1960-2003 years) Nakatsu Village Prefecture field municipal boundaries Kawabe-cho dragon village Inami-cho Minabegawa village Nakahechi 100 people 50 10 1 1960 of the self-employed made charcoal household Tanabe Oto Village kozagawa Nachikatsura town charcoal production the number of people in 2003 Hikigawa susami Koza-cho 0 20d self-employed made charcoal household Note) manufacturing charcoal number of people in 1960 to municipal statistics manual of the 1960 Census of Agriculture and Forestry (Wakayama Prefecture). Ltd. charcoal number of people in 2003 by a charcoal producer number of special forest products supply and demand dynamics investigation of Wakayama Prefecture. Technology lore 437 of charcoal by Yamamura migration of urban residents 1 households, 6 households those turning 18) in the same plum cultivation, which manufactured charcoal who has returned home to Hometown 1 household, unknown has become one household. Tanabe Akizugawa neighborhood, is also a similar trend. (A) mountain village migration of urban residents So what will that this reduction of such manufacturing charcoal who are replenished how. As already mentioned in Chapter 2, and the settlement policy of urban residents to the agricultural mountain village as part of Wakayama of Agriculture, Forestry and Fisheries administrative, technical guidance for the new entrants to those who blame coal industry is doing in each municipality, or settlement policy, that is done in each municipality, and to lead to new entrants to the manufacturing Sumi-gyo, is has become the training of leaders of Seisumi-gyo. According to the Wakayama Prefecture Kishu charcoal entrants material, 1989 (FY original) from 2004 Kishu charcoal new entrants reached 87 people, U-turn's 46% from urban areas to rural areas, cities Wakayama Prefecture capital of from the frequency J turn of 6.9% to the city limits, rural of I turn no urban areas from relatives has become 41.4%. New entrants number of to municipal Kishu charcoal is shown in Table 4, according to this, including 16 people Minabegawa village, etc. Nakatsu Village and Tanabe City, Oto village of new entrants to the Kishu charcoal often has it seen. On the other hand, looking at the area out sends the new entrants to the Kishu charcoal, Wakayama Prefecture in (46 people) than rather than the most multi-Keihanshin District adjacent, then it can be said that the Tokyo metropolitan area, and Fukuoka Prefecture often. Table 4 Kishu charcoal municipal new entrants number of municipalities name new entrants number of southern river village 16 in Tsumura 13 Tanabe City 12 large tower village 11 days location River Town, 8 river side-cho, 7 southern town 6 in the side road-cho 4 nachikatsuura 3 white beach Town 2 mark Minami-cho, 2 to of seen town 2 dragon god town two other towns and villages 11 Total 99 by Note) Wakayama Prefecture settled promotion Division documents. Minute of migrant number of Heisei first year to 14 years. Of 12 people was stopped manufacturing charcoal out of business, or the like. 438 Matsuyama University Journal 17 Vol. 2 No. 7 Kishu charcoal new entrants Hometown (1989 to 2003) 0 200d 50 people 10 1 Note) created from Wakayama Prefecture, agricultural and marine products settled Development Division provides materials urban residents of the mountain village charcoal technical lore 439 by immigration (c) conventional manufacturing charcoal form manufacturing of Kishu charcoal, either would had been done how conventional. 8, about 35 owns a forest of hectare, mainly ○ A 10 hectare · ○ Lee 9 at hectare of selection forest procure raw wood to have Akizugawa district shows the selection forest management of N's own mountain It is. The selection forest there was a 3 style of the weaker-moderate-intensity selective logging, FIG. 9 shows a selection forest of moderate degree among them. Moderate degree of selective cutting forests, 60-70% in HayashiTsumoru, 20-30% in the number, Medori diameter 4.5 or higher of the tree is subject to selective cutting. Regression year years 8-10, Hayashi-so form a three-stage forests. Selection forest is not cut down Yoyowaiki and middle aged trees, since harvesting period is short, as compared to the clear cutting forests, it was possible to obtain an increased yield of 50-60% in the same year. At the time, Kishu Bei length charcoal core production area in which was Akizugawa district of phillyraeoides of selective cutting technology, it said that was in the highest level 19 nationwide). However Wakayama Prefecture, Chubu of Yamamura, rather than intense the integration of forest land by large forest landowners, was a typical large forest landowners of appearance fabric 20) of Japan. Meiji after forest is integrated in such as firewood quotient of the coastal area, a lot of manufacturing charcoal who is a self-owned forests is narrow, it is inevitable to rely on wood to large forest landowners of firewood mountain, Shoko system 21) persons engaged there were many in Seisumi under the. Figure 10 illustrates the actual use of firewood mountain that put in Gaiyama that Mr. H of Ichiigawa village Minabegawa is Iriyama (bargain trees only). Area of Sumiyama about 5 hectare, production of charcoal is a mountain of about 1,000 bales (15), Sumigama and stay hut, Sade canal therefore blame charcoal who was Gaiyama, that are sequentially use. Until the 1960s, in the locality of Kishu charcoal is, Sumigama is a convenient place to collecting material of the mountains of phillyraeoides, convenient Toko in there is swamp water built into the furnace. The Every pot that was drilled in Sawa, wooden tools, etc., such as Every immersed in water, during the extinguishing of hard charcoal is watering its water to carbon ash, also emergency-proof have you and also to fire water It was used. Such as when staying hut of the seminal (Nerashi), when daily life there together, also became a resting place in Seisumi work. 440 Matsuyama University Journal 17 Volume No. 2 management of 8 Wakayama Prefecture N's selective cutting firewood forest (1965) 11 hectare forest 3 hectare of selective cutting firewood forest of 8 hectare cedar and cypress plantation of 2.5 hectare forest Akamatsu of - afforestation of cedar 9 hectare of selective cutting firewood forest 010 hectare of selective cutting firewood forest ® 2 hectare forest 1.2 hectare cypress plantation of 0.8 hectare of clear-cutting firewood forests ® ® C 0 500c river roads - the future of logging order charcoal kiln N's owned forests Note) Shigenori Shinohara (1967): types of manufacturing coal region of Shikoku, geography critic, I due to 40-11. Phillyraeoides miscellaneous 9 Wakayama Prefecture of selection forest Akizugawa sprouting 8 to ten years 8-10 years and eight to ten years forest types about '25 selective logging after two years of forest types of after the next selective cutting two years of forest types after next selective cutting two years Note) Shinohara Shigenori (1967): types of manufacturing coal region of Shikoku, geography critic, I due to 40-11. Urban residents Yamamura charcoal technology lore 441 by immigration Figure 10 Minabegawa village Ichiigawa of H's purchase mountain (sketch) Sa Sa de de de canal road Kyukamaato tail root Kyukamaato rack line Sawa support horse road The de road Eburitsubo stay hut Sumigama H's home Ogawa car road 442 Matsuyama Journal 17 Volume No. 2 Photo 7 Minabegawa village of mountains in Ichiigawa Sumigama (left) and Kyo-sho shop (far right) (March 2004 ) Photo 8 Minabegawa village Eburitsubo in Ichiigawa (March 2004) (d) current status of charcoal production Minabegawa village there is manufacturing charcoal's 2002 currently 37 people, charcoal production, the manufacturing charcoal toll your stomach, is a municipality's premier under Wakayama Prefecture. The author through 2003-2004, and visited the manufacturing charcoal person in each Sumigama, tried to survey about the actual situation and the daily life of manufacturing coal activities of manufacturing charcoal's. Survey number ranged in total five times, but was able to make the interview survey from manufacturing charcoal's inner 32 people. 11, the 32 guests (local made charcoal's 24 employees, new entrants 8 people from the urban areas) are those Sumigama and residence of, the raw wood mountain shown on the map. This mountain village by migration of urban residents technology lore 443 of charcoal to within wood mountain are building a Sumigama it was only manufactured charcoal's. Management and home relationship firewood mountain have purchased of his (purchased wood only), it is the time is shown in Figure 10. Along it Sumigama other than the national highway, located on the prefectural road, town road-Lindau, it I said to be located in a convenient point to carry the wood in the mini truck. The manufacturing charcoal who began to introduce a mini track is from around 1970, the Sumigama began primarily located along the road, that then is from 1980 around. Sumigama and manufacturing coal's residence are also those that are close to, but also to the greater are away from number 1. Sumigama is to located along the road that was off the beaten track, it is due to the fact that hate residents the smoke of charcoal in Seisumi work. Sumigama and wood mountain is generally away. It Seisumi's a none is forest owned by the distribution of Sumigama, housing and timber harvesting forests in 11 Minabegawa village Say coal's (2003) 678C 768c 603c 24 422c 4 24 22 22 28 29 28 2121 3 3 25 1 1 4 22 29 6 49 8 10 18 27 8 2620 1918 23 1615 14 6 27 9 26 20 10 10 17 2319 25 17 386c 7 30 15 30 413c 2 26 511c 499C of urban migrants Sumigama 339c 21 31 24 13 11 5 347c 13 9 Sumigama of local residents dwelling made of charcoal's 12 12 125c 1 created by the Note) field research 20 15 264c 0 2D wood Mountain (stumpage purchase) wood Mountain (Jiyama) national highway prefectural road, towns and villages road river foothills line number Seisumi show the party number (for the same made charcoal person, I have been using the same numbers in Sumigama, housing and timber harvesting forests both). 444 Matsuyama Journal No. 17, Volume No. 2 or, due to being a very small own. Ltd. charcoal person every time wood mountain to move, take a lot of money and effort if it is to rebuild the Sumigama. The Sumigama is no longer restricted to raw wood mountain, mini track is popular, it is because he became so can be transported to the raw wood is easily Sumigama. How to obtain the raw wood is the were purchased Offer mountain, manufacturing charcoal himself cut down, there is also intended to transport it to pottery in mini track, and Ru More things to buy from the village outside of the timber suppliers. In order to increase the Seisumi efficiency, rather than the logging and export of raw wood, it is better that depend on trees purchase, called extensible sales production of charcoal. (E) actual condition of new entrants of urban residents to Kishu charcoal production new entrants of urban residents to Kishu charcoal, when by Wakayama Prefecture settled Development Division of the article, 87 people in 1984 to 2004 I reached and reached U-turn · I turn together 87 people. New entrants often Wakayama Prefecture municipalities to Seisumi-gyo, it is a central mountain village area of Wakayama Prefecture Minabegawa village 22) in the Tsumura 23) Tanabe 24) Oto village, is where you have already pointed out . Table 5 summarizes the new entrants a lot of 4 municipalities new entrants before residential areas and migration year to Seisumi-gyo, such as immigration motive as list. Kishu Bei length new entrants prior to the previous dwelling place in charcoal , the Kinki metropolitan area centered on Osaka, many in the metropolitan area centered on Tokyo, then it can be said that the east sea area. Looking at the ages, from the elderly in excess of 70 years, it is a wide variety in Seisonen layer between them. Occupation in urban areas of the previous residential land multi- but over the Toki, computer engineer, banker-cram Photo 9 Tanabe Akizugawa Kishu charcoal Memorial Park (November 2003) before the Bussan Museum - Road Station -, beyond the museum urban residents of charcoal technology lore 445 by Yamamura immigration such as lecturer, conspicuous person who was engaged in high mental stress profession, other, was engaged in flow work specific work in the near-generation plant things often. Motivation that has been fascinated by the manufacturing charcoal of charcoal, which is often the person who is found are showed in flames burning bright red at the time of kiln out, in essence, is longing to life mountain village that was blessed with a natural, self-active in agriculture and forestry that aim the salt of life to those who want to can be said to be overwhelmingly large. If you like this look, the past, the movement of residents seeking employment in metropolitan areas from rural areas was a mainstream, now reverse from the metropolitan area is the reflux of the population to rural areas can be seen. Than live in strict management society is employment in large companies of big cities rather than, is self-supporting with naturally blessed rural, urban residents to find a reason for living to leisurely late from Succoth is increased to ensure that are and it can be read. It is one of the feature is also the person who is more likely to enter the village along with a companion. Successor of Hometown of the mountain village is the worrying about lack daughter-in-law is a contrast. Is Irimura along with a good mate from the metropolitan area, plight is caused envy the Seisonen's single of Hometown
đang được dịch, vui lòng đợi..


, according to supply and demand for forest products research too at 436 Matsuyama University Journal, Vol. 17, No. 2, and making the number has decreased in 197. Fig. 6 , of charcoal production in Wakayama Prefecture municipalities in recent 40 years in the south of the making of the reduction is shown. , and a large number of cases in the village who s-61n making in business world of making at the belt 111 and , , 48 households in 1999 and has been cut in half and households in 2004., between 1999 and 2004 , dropped from charcoal-making business and household coal is made to elderly person 10 households , 4 the dies , municipalities making the reduction of Fig. 6 of what it is, and the disease (1960 2003 )
stress at Nakatsu village world cities at Prefecture world Ryujin village Kawabe, too too too too at inami town at the village at nakahechi s-61n stress too too, at 100 at 50 at 10
1, 1960, self-employed households making Tanabe at at at at at at bet kozagawa town oto is, too.2003 charcoal production number in town at the Koza town susami town too at 0 20 d stress) stress 1960 1960, making the number of cities, towns and villages in agriculture and forestry census and Statistics (Wakayama Prefecture) making self-employed households. 2003, by making the number of special forest products research and production of charcoal. The bincho charcoal technology transfer is the effect of urban residents moved to rural households in the first , plum turning 18) household , one household one , 1, he returned to his birthplace in making person and household.Tanabe city near the akidzugawa district is in the same direction. 2-evolution) of urban residents and rural immigration. Then , are how to decrease the making of it. , already described in the second chapter , resettlement policy and urban residents to rural as part of the administration of the agriculture, forestry and fisheries technical guidance and , for new entrants to the municipalities in the industry in making a settlement or policy that , , place the city of coal industry leads to new entrants to the ,The training and making industry. , of Wakayama Prefecture charcoal entrants and materials (1989) from new entrants charcoal reached 87 in the name of the , 41.4 and turn from urban to rural U who turn to turn J at. Area of Wakayama Prefecture and 6.9 46 from urban area and urban area or not, and relatives of I. At the , municipalities, the number of new entrants to the charcoal in Table 4 shown in this ,Village s-61n 16 people including , Tanabe Nakatsu village, many new entrants in the village and oto into charcoal. One of the , , area and new entrants to send charcoal in Wakayama Prefecture (46), which was the highest in the keihanshin area adjacent to the outside of the , metropolitan area has many , Fukuoka Prefecture. Municipalities of charcoal at the table 4 new entrants numbers of cities, towns and villages name number of new entrants River south of the village village 16 in Tsu City Tian 12 13 side at the large tower 11 days at the village on the river town.River side, at the south side of town in line 6, 4, 3, 2, 2, mark at the white beach, South to the town of 2 Dragon God and at the other with the indicator 11 99 note) in Wakayama Prefecture settlement promotion division. For years the number of persons in 1989. Stop making such as business, one in 12 patients. Matsuyama University at 438 is review, Vol. 17, No. 2 in Fig. 7 is a novel stress charcoal entrants from 1989 to 2003) at at at at at at at at at 200 stress
d 0 50 10 is 1.Note: data provided by agriculture, forestry and Fisheries promotion division, settled by SEM is the creation of urban residents in rural transfer - YouTube 439) according to the conventional production of charcoal charcoal at the ,? And how. Fig. 8 , owns about 35 hectares of forest , in selection cutting forest management of mountain area is mainly N of akidzugawa financing selection cutting forest in a 10 hectares and a 9 hectares. Weak selection cutting forest and moderate degree of three modes of selective cutting intensity was ,Fig. 9 shows a moderate degree of selection cutting forest. , selection forest trees and forest in a moderate degree of more than 20 to 30%, and 4.5 audience has a diameter of 60 to 70%, and the number of selection cutting. Regression in 8 to 10 years , makes three forest forest. In the age of young trees and cutting trees without the , selection cutting forest felling cycle is short, so , clear-cutting forests in comparison , could get 50 to 60 percent of the crop in the same year. At the time of the selection of the , , Holm was akidzugawa District Technology of coal production for long core
stress at Nakatsu village world cities at Prefecture world Ryujin village Kawabe, too too too too at inami town at the village at nakahechi s-61n stress too too, at 100 at 50 at 10
1, 1960, self-employed households making Tanabe at at at at at at bet kozagawa town oto is, too.2003 charcoal production number in town at the Koza town susami town too at 0 20 d stress) stress 1960 1960, making the number of cities, towns and villages in agriculture and forestry census and Statistics (Wakayama Prefecture) making self-employed households. 2003, by making the number of special forest products research and production of charcoal. The bincho charcoal technology transfer is the effect of urban residents moved to rural households in the first , plum turning 18) household , one household one , 1, he returned to his birthplace in making person and household.Tanabe city near the akidzugawa district is in the same direction. 2-evolution) of urban residents and rural immigration. Then , are how to decrease the making of it. , already described in the second chapter , resettlement policy and urban residents to rural as part of the administration of the agriculture, forestry and fisheries technical guidance and , for new entrants to the municipalities in the industry in making a settlement or policy that , , place the city of coal industry leads to new entrants to the ,The training and making industry. , of Wakayama Prefecture charcoal entrants and materials (1989) from new entrants charcoal reached 87 in the name of the , 41.4 and turn from urban to rural U who turn to turn J at. Area of Wakayama Prefecture and 6.9 46 from urban area and urban area or not, and relatives of I. At the , municipalities, the number of new entrants to the charcoal in Table 4 shown in this ,Village s-61n 16 people including , Tanabe Nakatsu village, many new entrants in the village and oto into charcoal. One of the , , area and new entrants to send charcoal in Wakayama Prefecture (46), which was the highest in the keihanshin area adjacent to the outside of the , metropolitan area has many , Fukuoka Prefecture. Municipalities of charcoal at the table 4 new entrants numbers of cities, towns and villages name number of new entrants River south of the village village 16 in Tsu City Tian 12 13 side at the large tower 11 days at the village on the river town.River side, at the south side of town in line 6, 4, 3, 2, 2, mark at the white beach, South to the town of 2 Dragon God and at the other with the indicator 11 99 note) in Wakayama Prefecture settlement promotion division. For years the number of persons in 1989. Stop making such as business, one in 12 patients. Matsuyama University at 438 is review, Vol. 17, No. 2 in Fig. 7 is a novel stress charcoal entrants from 1989 to 2003) at at at at at at at at at 200 stress
d 0 50 10 is 1.Note: data provided by agriculture, forestry and Fisheries promotion division, settled by SEM is the creation of urban residents in rural transfer - YouTube 439) according to the conventional production of charcoal charcoal at the ,? And how. Fig. 8 , owns about 35 hectares of forest , in selection cutting forest management of mountain area is mainly N of akidzugawa financing selection cutting forest in a 10 hectares and a 9 hectares. Weak selection cutting forest and moderate degree of three modes of selective cutting intensity was ,Fig. 9 shows a moderate degree of selection cutting forest. , selection forest trees and forest in a moderate degree of more than 20 to 30%, and 4.5 audience has a diameter of 60 to 70%, and the number of selection cutting. Regression in 8 to 10 years , makes three forest forest. In the age of young trees and cutting trees without the , selection cutting forest felling cycle is short, so , clear-cutting forests in comparison , could get 50 to 60 percent of the crop in the same year. At the time of the selection of the , , Holm was akidzugawa District Technology of coal production for long core
đang được dịch, vui lòng đợi..


Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.
- hư
- theo bạn loại phương tiện truyền thông p
- hãy giữ ấm cho cơ thể
- chúng ta đi sắm sửa quần áo đẹp để đi th
- 1- CONCEPT CHÍNH (trình và thuyết phục n
- the items named below
- tôi đã cộng số liệu tháng 8 và tháng 10
- the most famous diary in english was wri
- Test Reference Number:
- tôi đang tắm
- disclosure reveals the most recent three
- chuột máy tính bj hư
- giấy đề nghị xuất kho
- đổ bỏ xà bần
- kính thưa quý vị,hôm nay tôi sẽ nói cho
- Năm nay tôi 23 tuổi
- HÊ THỐNG CHIẾU SÁNG
- 合闸
- This recovery phase is not necessarily h
- the most famous diary in english was wri
- (泥棒、痴漢、不審者の注意
- mì gói
- bạn đang làm gi
- grading